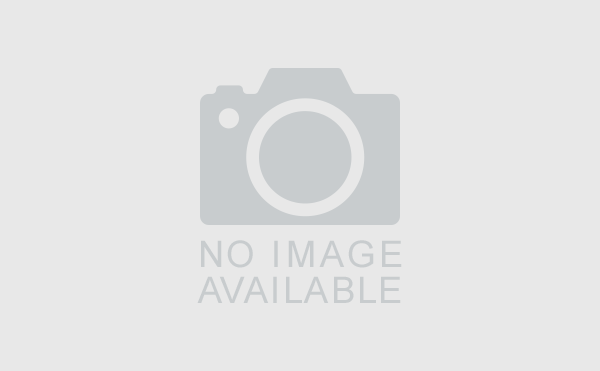電気系技術者が中途採用できない5つの理由|採用に悩む企業が今とるべき選択肢とは?

こんにちは!
横浜を拠点に製造業向けの人材派遣を行っているリアスコです。
「電気系の技術者が中途で採用できない」
「求人を出しても、まったく応募がない…」
そんなお悩みを抱えていませんか?
私たちは30年以上にわたり、製造現場に電気・制御系の技術者を派遣してきましたが、ここ数年で「人が採れない」というご相談が明らかに増えています。
とくに、中途採用においては
- 求人広告を出しても反応がない
- スカウトメールを送っても既読すらされない
- 紹介会社に依頼しても、紹介される人材とニーズが合わない
といった“採用の行き詰まり”を感じている企業が非常に多いのが実情です。
採用できなければ現場が回らず、既存社員の負担が増え、最終的には納期遅れや取引先との関係悪化にまでつながりかねません。
今や「技術者が採れない」は、単なる人事部門の課題ではなく、企業の事業継続に関わる重要課題です。
そこで本記事では、
- なぜ今、中途採用がこれほど難しくなっているのか
- 応募が来ない/決まらない根本的な原因
- そのうえで、どうすれば即戦力人材を確保できるのか
を明らかにしながら、「派遣」という現実的な解決策についてもご紹介します。
「このまま採用活動を続けても、本当に人が採れるのか…?」
そんな不安を抱える中小企業の経営者・採用担当者の方に、少しでもヒントとなる情報をお届けできれば幸いです。
第2章|中途採用で電気系技術者が採れない5つの理由
中途採用で電気系技術者が集まらない原因は、決して一つではありません。
私自身、現場と採用の両方を見てきた立場から言えるのは、「待っていればそのうち応募が来る」という時代はもう終わっているということです。
ここでは、特に中小企業が直面しやすい“採れない理由”を5つに絞って解説します。
1. 人材の絶対数が少ない
電気設計や制御設計、設備保全といった分野は、若手の人材が非常に限られています。
少子化や大学の理工系離れも影響し、今の20〜30代で電気系に進んでいる人は、想像以上に少ないです。
また、電気系のベテラン技術者はすでに企業に囲われていたり、フリーランスや顧問として独立しているケースも多く、中途市場にほとんど流通していません。
そもそも「採用対象になる人材が少ない」ことが、採用難の最大の要因です。
2. 求職者は“企業の名前”と“待遇”でまずふるいにかけている
現実として、求職者の多くは求人票の「社名」「給与」「年間休日」で応募を判断します。
たとえ仕事のやりがいや現場の雰囲気が良くても、条件面で不利な中小企業は候補から外されやすいのが現実です。
採用市場では、企業の知名度やブランド力が“第一フィルター”になっています。
技術や人柄ではなく、入口の時点で戦えていない──
これは多くの企業が気づきにくい盲点です。
3. 実務経験者は“転職市場に出てこない”
「実務経験5年以上」「PLC経験必須」など、即戦力を求める採用条件を出している企業は多いですが、実際にその条件に合致する人は、今いる会社で重宝されていたり、転職を考えていないケースが大半です。
つまり、求人広告を出しても本当に欲しい人材には届いていないのです。
転職市場に出てこない人材をどうやって採るか——
ここに中途採用の限界があります。
4. 応募があっても「ミスマッチ」で終わる
「制御設計の経験があります」と履歴書に書かれていても、いざ面接してみると
「うちの設備には合わないかも…」と感じたこと、ありませんか?
制御設計といっても、人によって得意な分野やスキルに大きな差があります。
たとえば、
- 三菱のPLC(MELSEC)には強いけれど、キーエンスやオムロンは使ったことがない
- ラダーまでは書けるけれど、タッチパネルや画面設計は未経験
- 新規設備の立ち上げよりも、既存設備の改造を多く経験している
といった具合に、“制御経験あり”の中身は人によって全然違うんです。
中途採用では、こうした技術の違いや現場での対応力を、書類と面接だけで見極める必要があり、結果的に「合わない」と判断して不採用になるケースが多いのが実情です。
採用活動にかけた時間や工数が、そのままロスになってしまう――
そんな状況に陥っている企業さまは少なくありません。
5. 採用活動にかけられる“工数”がそもそも足りない
中小企業では、採用専任の担当者がいないことが多く、人事・総務が他の業務と兼任していたり、現場の責任者が面接対応をしているケースもあります。
そうなると、書類選考や面談、条件交渉などに十分な時間を割けず、対応が後手に回ってしまうことも。
結果的に、良い人材をタイミングよく逃してしまったり、応募者との連絡が途切れてしまう…という事態になりがちです。
補足:「採れない理由」は企業の問題とは限らない
ここまでお話しした5つの理由は、どれも企業が悪いから採れないという話ではありません。
むしろ、市場全体の構造が変わっているため、従来のやり方では成果が出づらくなっている、ということです。
では、この状況をどう乗り越えていくべきか?
次章では、採用がうまくいかない企業によくあるケースと、打開策として注目されている「派遣」という手段についてお話しします。
第3章|頑張っても採用できない企業に共通するパターン
「求人媒体にも出した」
「スカウトも送った」
「人材紹介にも頼った」
それでも採用できない――。
そんな企業には、いくつかの“共通点”があります。
ここでは、私たちリアスコがこれまで現場で見てきた「がんばっているのに採れない企業」の特徴を、いくつかご紹介します。
1. 採用チャネルは使っているが、“母集団”ができていない
大手求人サイトや人材紹介を活用していても、そもそも電気系技術者がそこにいないことも珍しくありません。
ターゲット層が違えば、どれだけ広告にお金をかけても反応はありません。
特に、実務経験者は「能動的に応募する」よりも、「声をかけられて動く」タイプが多いため、求人広告だけでは不十分になっている可能性があります。
2. スカウトメールを“営業文”として送りすぎている
「スカウトメールを送っても返ってこない」これはよくあるご相談です。
内容を見ると、自社のアピールばかりで、求職者の立場に立ったメッセージになっていないことがよくあります。
たとえば、「急募」「アットホームな職場」などの定型文ばかりでは、応募者の目には止まりません。
必要なのは、「あなたのこの経験に興味があります」という個別の接触です。
3. 紹介会社に任せきりで終わっている
紹介会社に依頼している=安心、ではありません。
マッチングの質や紹介スピード、求職者のフォロー体制は会社によって大きく異なります。
また、自社の魅力や課題をきちんと伝えられていないと、紹介される人材もピントがズレてしまいます。
紹介会社とは“共同作業”が必要なんですが、ここがうまく機能していない企業も多いのが実情です。
4. 「正社員前提」にこだわりすぎている
今は「すぐに正社員で採用」というスタイルにこだわると、人材確保のスピードで出遅れてしまうケースがあります。
現場は人が足りない。けれど正社員採用には時間もコストもかかる――
そんなときに、「派遣」や「紹介予定派遣」といった選択肢を取り入れている企業は、必要なときに必要な人材を確保できている印象です。
5. 採用に「現場の声」が反映されていない
技術職の採用では、現場が「この人ならいける」と思えるかが非常に重要です。
ところが、実際の選考で現場がノータッチだったり、「後から一度会ってみて判断する」という流れになってしまうと、採用のスピード感やマッチ度が下がってしまうことがあります。
現場の声から導く、次の選択肢とは?
こうしたパターンに心当たりがある場合、採用のやり方そのものを見直すタイミングかもしれません。
特に、
- 応募者がいない
- 応募はあっても採用に至らない
- 正社員にこだわって時間ばかり過ぎている
こうした状況が続いている企業ほど、「派遣」という形を柔軟に取り入れることで、現場を止めず、事業を前に進める道が見えてくることがあります。
次章では、その「派遣」という選択肢が、今なぜ注目されているのかを詳しくお伝えします。
第4章|採用に悩む企業が「派遣」という選択肢に切り替える理由
これまで「正社員として中途採用する」ことを前提に採用活動を続けてきた企業が、近年「技術者派遣」という選択肢に切り替えるケースが増えています。
なぜでしょうか?
その理由は一つではなく、スピード・柔軟性・ミスマッチ回避という複数のメリットがあるからです。
ここでは、私たちリアスコが現場で感じてきた“実際の導入理由”をもとに、技術者派遣という選択肢の魅力をお伝えします。
1. 即戦力を確保できる
派遣の最大のメリットは、「いま必要な人材を、必要なタイミングで現場に入れられる」ことです。
中途採用では、求人票作成→掲載→応募→面接→内定→入社までに2〜3か月以上かかるのが一般的ですが、派遣なら早ければ1〜2週間で配属可能なこともあります。
現場が止まりそうな時、短納期の案件が続く時期など、「すぐに人が欲しい」というニーズにしっかり応えられるのが、派遣という選択肢です。
2. 採用コスト・失敗リスクを抑えられる
中途採用には、求人広告費や人材紹介料、入社後の教育・定着支援など、見えづらいコストが多くかかります。
そして何よりも、「せっかく採用したのにすぐ辞めてしまう」というリスクも無視できません。
派遣なら、こうした初期コストや採用失敗リスクを大きく抑えることができます。
万が一合わなかった場合も、契約更新を見送るだけで済み、組織全体への影響も最小限にできます。
3. 自社採用と並行できる“つなぎ”として使える
「いずれは正社員を採用したい」という企業も、派遣を“つなぎ”として活用することができます。
派遣で現場の稼働を確保しながら、水面下で正社員採用活動を続ける――
そんな柔軟な戦い方ができるのも、派遣という手段の強みです。
また、紹介予定派遣(一定期間派遣として勤務し、双方合意で正社員化)という形を選べば、ミスマッチリスクをさらに下げた採用も可能です。
4. 採用よりも「現場での即戦力」を重視する企業に最適
- 新しい設備を導入したが、操作・立上げできる人がいない
- 現場のリーダーが退職し、教育できる人材がいない
- シーケンスやPLCが扱える人材が一時的に必要
こうした「この業務だけは止められない」という現場の事情に応えるには、派遣のスピード感と柔軟性が非常に有効です。
特に、経験者が必要な短期プロジェクトや試作・立ち上げ業務では、派遣のほうが圧倒的に適していることが多いです。
5. 正社員よりも「早く」「的確に」現場を支えることができる
「派遣=即戦力」とよく言われますが、実際、派遣でご紹介する人材は実務経験を積んだ技術者が多いのが特徴です。
私たちリアスコでは、派遣先の技術レベルや業務内容に応じて、事前にスキルや経験を確認したうえで人選しますので、現場での早期戦力化が実現できます。
「人がいないからとりあえず誰か入れる」ではなく、
「必要なスキルを持った人材を、適切なタイミングで投入する」
――これが、派遣の本質的なメリットです。
まずは派遣という選択肢を“知る”ことから
中途採用がうまくいかないとき、「採用方法を変える」という選択は、決して妥協ではありません。
むしろ、今の事業を守り、次のチャンスを逃さないための前向きな決断です。
第5章|採用に限界を感じたとき、まず何をすべきか
ここまでお読みいただきありがとうございます。
電気系技術者の中途採用が難しくなっている背景と、その理由、そして派遣という現実的な選択肢についてお話ししてきました。
では、実際に「うちも採用が厳しいな」と感じた時、まず何をすべきか?
結論から言うと、それは「自社の現場に本当に必要な人材像を見直すこと」です。
1. 求める人物像を、正社員前提で固めすぎていませんか?
「35歳以下」「PLC経験5年以上」「設備導入まで対応可能」といった条件が、現実の採用市場にマッチしているか?
この点を一度フラットに見直すことをおすすめします。
今の状況では、すべての条件を満たす人材を正社員で採用するのは、ほぼ“奇跡待ち”に近い状態です。
条件を緩めるのではなく、アプローチ方法を変えることが必要です。
2. 正社員採用と、派遣の併用という考え方を取り入れる
「ずっと正社員で回してきたから」「派遣は初めてだから」
そういった声もよくいただきます。
ですが、今は「とにかく正社員だけでやりくりする」という時代ではありません。
必要なところには派遣で即戦力を補い、正社員はじっくり育てる。
柔軟な人材戦略こそ、現場を守り、事業を前に進めるカギです。
3. まずは相談してみるところから始めてください
「派遣を使うかどうかはまだ決めていない」
「どういう人がいるのか知りたい」
それで構いません。
私たちリアスコでは、導入前のヒアリングをとても大切にしています。
設備構成、現場人数、既存社員のスキル構成などを確認したうえで、本当に必要な人材像と、その確保手段をご提案いたします。
派遣か、紹介予定派遣か、それとも別の方法か。
まずは、選択肢を持つことから一緒に始めてみませんか?
お問い合わせはこちらから
「電気系の技術者が本当に足りない」
「今のやり方では採用が進まない」
そう感じているご担当者さまへ。
一度、私たちリアスコにご相談ください。
現場出身の担当者が直接ヒアリングし、貴社の課題に最適な形をご提案いたします。
中途採用に限界を感じた今こそ、派遣という選択肢を。
リアスコがお手伝いします。
お気軽にお問い合わせください。045-717-8868受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ